| ←124鞍目 | 125鞍目・ハミ受けができる? (2003.6.1 あきる野・日の出乗馬倶楽部) |
126鞍目→ |
|---|---|---|
|
前日の土曜日、日の出乗馬倶楽部のすぐそばにあるロッジに宿泊し、乗馬仲間と泊まり込みの宴会。本来なら土曜に1鞍乗って、宿泊して日曜も1鞍、というつもりだったのですが、なんとこの日は気の早い台風がきていて土砂降り。でもロッジの予約はしてしまっているので、宴会は決行しました。翌朝起きてみると、またぽつぽつ雨が降っていましたが、先に起きていたQさんによると「これから晴れるよ」とのこと。そうね、と安心して2度寝。だってまだ、ゆうべの酒が抜けてないし(笑)。 ふたたび起きたときには、曇ってはいましたが雨は上がっていました。11時の予約だったので、10時すぎにロッジを出て倶楽部へ。あらかじめキュロットをはいて現れた私を見て、倶楽部のママさんが「あら、もしかして直接ご出勤かしら?」ふだん電車で通っている私が、キュロットをはいて倶楽部に入ってくることなどあり得ないので、そりゃバレて当たり前。いや、別にバレたっていいんだけど。ホワイトボードを見ると、騎乗馬はアルフォンスです。 昨日の雨で、馬場はまだ水っぽい(でも水はけが良いので、ぬかるんではいません)ので、革長靴はやめてチャップスをつけ、拍車をつけていると、いつのまにかレッスン15分前。やばいやばい、アルの馬装には時間がかかるのに。急いで馬房に向かいます。 馬房の扉ごしにアルフォンスに声をかけるまでもなく、アルは扉に鼻をくっつけて、私のほうをじーっと見ていました。さて、アルを馬房から出すのは第1の難関。いつも無口をつけるところで、無口に噛みつかれて遊ばれるので、今日はあらかじめ引き手を口元に差し出します。当然アルフォンスはそれをくわえて遊び出すので、その隙に馬の左側に回り込み、無口をかけます。普段なら、それでも無口か私に噛みつこうとするのに、今日はやらないな。意外にいい子じゃん。 そこから馬繋場に引いていこうとする間に、いつものように立ち止まるアルフォンスですが、たまたまそこにいたEさんにお尻をたたいてもらったら素直に歩き出しました。馬繋場につなぎ、まずはこの虫除け馬着を脱がせなければ。 馬着の留め具は胸前に3つ、でもここって一番アルフォンスが噛みにきたい場所なので、まずは無口の頬革部分を片手でつかんで噛まれないように防御。右手だけで留め具を外すのも至難の技ですが、噛まれるよりはマシ。でも意外にも、アルフォンスは噛みにきません。まぁ、少しでも噛みそうな気配を見せたら、私も「アル? 」とひとにらみして牽制してるけど。一度、噛もうとして振り返ったアルに肘をかすられましたが、こっちも学習してるんだよーん。 蹄の裏掘り、ブラシ。ブラシの間は意外にもおとなしくしているアルフォンス。嫌がるかなと思った首周りや帯径も大丈夫でした。ブラシを終わり、前肢にプロテクターを着けて、次は装鞍。アルフォンスの鞍がなかったのでK野さんに聞くと、「じゃあ僕の使っててください」ということで、K野さんの自鞍を借りて着けます。腹帯を締め、鐙の長さを調節していると、K野さんがアルフォンスにハミをかけはじめました。時間がないからということだろうけど、最大の難関をやってもらっちゃった。じゃあその間に、と思って、馬繋場の前に置いている鞭とグローブを取りに行き、アルのところに戻ろうとすると、K野さんがそのままアルを馬場へ連れて行こうとするところでした。「僕連れて行きますね、噛むから」最後の難関もやってもらっちゃった。 馬場の中央、あらかじめ踏み台が置いてあるところでアルフォンスをとめてもらい、そのまま補助をうけて騎乗。K野さんに腹帯を締め直してもらい、鐙の上に立ち上がってみると、「これはちょっと長いんじゃないかしらぁ」「そう? 別にいいんじゃないかしらぁ」と私の口調を真似てK野さん。「でもさー、見てよ、私今これで立ち上がってるつもりなんだよ」股がぜんぜん鞍から離れないんだって。K野さんも苦笑して、「じゃあ1穴だけですよ」と短くしてくれました。 今日の部班はロゼッタ、ウィンダム、ハイセイコーJR、アルフォンスの4頭。そのうち、ゆうべの宴会組3名。「二日酔いの人、いますかー」ってK野さん、自分だって睡眠不足のくせにぃ。「じゃあ準備のできた人から蹄跡に出て歩いててください」ということで、左手前で蹄跡を歩き始めます。 そこへ、ラチの外から見ていたQさんが「ちょっと待って、左前のプロテクターが外れそう」と言うので、馬を止めてプロテクターをつけなおしてもらいました。「これ、上下間違ってるね」というのは、プロテクターのマジックテープになっている部分とそうでない部分の重ね方の上下を間違っていて、接着部の面積が狭くなっていたということです。「あ、じゃあ右前も間違ってると思う」そっちもやりなおしてもらい、改めて常歩。 全員が蹄跡で常歩を始めたところで、K野さんが「じゃあロゼッタ先頭でいきますからねー」うわ、かわいそ。よくよく見るとこの部班、どの子も先頭では動きたくない子ばかりで、他馬の後ろならそれなりによく動けるのに、先頭になるとぱたっと止まったりする子だらけです。 乗っているうちに日が差してきて、湿った馬場が蒸されて暑くなってきました。アルは「暑いよー、虫がヤダよー」と言っては止まろうとする。その都度拍車をいれると、まぁそのときは素直に言うことを聞くのですが、すぐ忘れる。なかなか歩度が伸びないので、ショートカットして行きます。 「いいですか、手綱ちゃんと持って。速歩いきますよ」速歩を出して行くと、ちゃんと走れるじゃん。速歩の巻き乗りも止まることなく、けっこういい感じ。 「ハミ受けさせて、頭下げさせてくださいね」一応前に習ったとおり、右、左と交互に手綱を握ります。「軽速歩なら、立ったときに外方、座ったときに内方を握るんです」あっ、方向があったのか。左右交互ならどうでもいいんだと思っていたけど、そりゃそんなわけないな。軽速歩で立つ、座るをやりながら、手綱を握っていきますが、なーんとなくタイミングがずれる感じで、うまく行きません。当然アルの頭も下がらない。 一度常歩に落とし、K野さんがそばをついて歩きながら教えてくれます。「常歩だと、馬の前肢が出たほうを握るんです」あ、なるほど。それが軽速歩なら、外方が前に出たときに立つわけだから、立つときに外方を握るっていうのは理にかなってるわけだ。肢が出たほうを抑えるっていうのは、馬が前に出ようとする力をためるのに効果的っていうことなのかな。 言われるままに、ずーっと右、左と交互に握りつづけているのですが、アルの頭は下がりません。もっと握るのかなー、と思って強くしてみますが、「いきなり引っ張らないで、やさしくね」うむむ、難しい。「イメージとしては、ハミをひっぱるんじゃなくて、ハミを下に下げるんです」ふぅん。以前ボスに聞いた話だけど、JRAのT元調教師が、「馬のハミっていうのは、長いお箸の先でお豆腐(豆だったかも)をつまむのといっしょ」と書いていた、という話を思い出しました。お箸で、こわれやすいものをつまむとき、人間の意識は指ではなくて箸先にあるでしょ? 手綱でハミを操作するのもいっしょだよ、という話なのです。 K野さんがずっといっしょについて歩いてくれているのですが、なかなかアルの頭を下げさせることができません。するとK野さんが、アルのハミに指をかけて、ちょっと下に下ろしました。すると、すーっと頭が下がり、きれいに首が丸くなります。おお。「下げる」のきっかけを、馬のほうも待ってただけなのかも。すまんねぇ、うまく下げさせてやれなくて。「頭が下がったら、ひじの動きが大事だってことが分かるでしょ。頭が下がってるぶん手綱がゆるくなるんですから、ひじで調節してやらないと」拳だけで調節できないなら、ひじに逃がすんだ。先日のレッスンでさんざんひじを引かされましたが、こういうことなんだなぁ。 「じゃあ速歩で」速歩発進すると、またアルフォンスの首が上がってしまいます。それを一生懸命、前肢が出たほうの拳を握りながら速歩。ついに、少しですがアルの頭が下がりました。「これは握るのやめていいの?」「いや、もうちょっと頑張って」と言っているそばから、アルの頭が上がってしまいました。すっごく微妙な均衡を踏み外した気分だ。 「ロゼッタ以外、蹄跡の内側で輪乗り。ロゼッタ、蹄跡で駈歩」K野さんを中心にした同心円を描きながら、蹄跡のロゼは駈歩、内側の3頭は速歩。ロゼが蹄跡で駈歩をしている間、馬場の内側で輪乗りをしながら、そのままハミ受けにトライしつづけます。なかなか上手くはいかないのですが、K野さんは私がハミ受けの練習を続けていることが分かったようで、ロゼにつづいてて蹄跡に出たJRの駈歩を見ながら私の速歩も見ているみたい。「アルフォンス、もっと外に出して。内方ちゃんと使って」ちょっと脚がおろそかになっちゃったりして。アルもそろそろ飽きてきたのか、速歩しながら虫を追って後肢を跳ね上げたりします。 JRの駈歩が終わり、「次アルフォンス、蹄跡から駈歩。左手前で」ずーっと馬をつめたまんまだったので、たぶん出やすいだろう。蹄跡に出たところから駈歩の扶助を出すと、1歩だけ駈歩を出そうとしたのですが、そのまま速歩に落ちました。あれー、アルって駈歩が出ればちゃんと続く子なのに。 もう一度トライしますが、出なくはないけどなんだか出にくい感じ。K野さんに「手綱もう2センチ伸ばして」と言われ、そうか、首を固めすぎてたんだ。手綱をこころもち緩めて、もう一度隅角から駈歩発進、よしちゃんと出た。でも今日は隣の馬場との仕切りラチがないので、ちょっと外に出しすぎてふくらみすぎ、鏡の前の隅角に入るのが難しいかも。なんとか曲がれはしたのですが、そんな気持ちが伝わってしまったのか、坂を上りきるのがしんどかったのか、アルフォンスが速歩に落ちてしまいました。ちぇ。 「じゃあ半巻きして、手前換えましょう」右手前って、アルフォンスは少し苦手かもしれない。先日反対手前の駈歩をやられたのも右だったし、相方はアルの右手前駈歩は出しにくいと言うし。少し気合いを入れて、駈歩発進。最初はやっぱり速歩が出てしまったのですが、もしかしてこのまま拍車を使ったら駈歩になるか? と思って試してみようとしたら、すかさず「いい加減に出しちゃダメ〜」とK野さんの声が飛んできました。うひょ。 常歩に落として、再び駈歩発進。今度は素直に発進してくれたし、反対駈歩でもないよな。しかし、半周くらい駈けたところで速歩に落ちてしまいます。 「鞭外方に持ってください。鞭がふらふらしちゃってると、馬がびっくりしちゃいますからね」ああ、今のバタバタした感じの止まり方はそういうことなのか。右手前なので、鞭を左手に持ち替えて駈歩発進。きれいに発進しましたが、隅角ごとにスピードが落ちそうになる。「内方離しちゃダメですよ、ちゃんと使って」ロゼッタと違って、腹回りがしっかりしている(いや、アルが太ってるわけではなく、ロゼが痩せすぎなのです)アルフォンスは、拍車がちゃんと当たっている感覚があります。これは私の体格とアルの馬格の相性かもしれないけど。隅角に近づいたら、内方の拍車をちゃんとこすりつけるつもりで追うと、ちゃんと続いた。けっこういい感じだし。 しばらく駈けて、「じゃあもう1度半巻き」左手前に戻って、駈歩発進。今度はきれいに発進できて、K野さんも「そうそう、今いい感じで座れてますよ」と言ってくれる。確かに鞍からお尻が離れないし、駈けていて楽。でもやっぱり隅角でスピードが落ちそうになるのですが、「拍車使って、さっきと同じですよ」さっき、右手前で拍車が使えてる感覚があったの、K野さんが見ててもわかってくれたのかな。でも左手前だと、右手前ほどうまくかかとが使えない感じ。そのまましばらく駈けて、鏡の前の隅角でまたもやふくらみすぎて、曲がりきれないなーと思ったのですが、首を内に向けるとどうにま曲がってはくれました。でも駈歩を続けることはできず、速歩に。 「はい、いいですよ。手綱伸ばしてそのまま歩かせてください」時計を見ると、もうレッスン終了時間でした。しばらく歩かせて、馬場中央に馬を並べ、挨拶。下馬して、アルフォンスを引いていきます。 馬繋場までまったく噛まれずに到着することができ、「噛まれなかった?」と周りに聞かれたので、「虫が気になってそれどころじゃないんだって」とアルを代弁しておきました。夏になると虫が気になるアル、乗りにくくはなるが噛まれないのは助かるな。今日はアルは午後もお仕事があるので、蹄の裏掘りだけして馬房へ戻します。 レッスン終了後、I野先生にお呼び出しをくらいました。なんだろー、と思ってクラブハウスへ出頭すると、7月に受験する検定試験の話。今年から全乗振の規定が変わったということで、2級から日馬連B級への移行システムが今までは障害・馬場2級の両方をとらないと移行できなかったものが、障害2級だけでB級に移行できることになったそうなのです(馬場のB級に、なんで障害2級だけで移行できるんだという疑問もありますが)。つまり、2級障害をとれる人間は2級相当の馬場も修めていると見なされるわけです。2級で馬場をやらなくていい分、3級馬場のレベルが引き上げられたということでした。馬場をやっていきたい私には、釈然としないシステムになってしまった感があります。 そんなわけで、当初の予定では7月に3級を受験するはずだったのですが、3級が難しくなってしまっていて、K野さん曰く「250鞍は乗ってないと」ということに。今やっと125鞍、250鞍っていつじゃー。「でもせっかくここまで頑張ってきたんだから、7月に受験するのは4級にしたらどうだ」というI野先生のお薦めに従って、4級を受験することになりました。 |
||
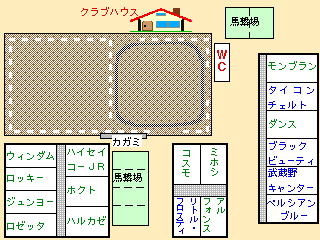 ↑日の出乗馬倶楽部の見取り図 (緑字:貸与馬、青字:自馬) |
||
| ←124鞍目 | 126鞍目→ |