| ←126鞍目 | 127鞍目・下げて、下げて (2003.6.7 あきる野・日の出乗馬倶楽部) |
128鞍目→ |
|---|---|---|
 おおっ、ちょっとだけど屈撓してるよ!! これで肘が突っ張ってなければねぇ、私。 |
昼食休憩をとって、14時から本日の2鞍目。騎乗馬はなにしろアルフォンスなので、馬装に時間がかかることは間違いない。少し早めに馬房へ向かいます。 アルフォンスは馬房の中で虫除けの薄手の夏馬着を着て、扉越しにこっちを見ていました。扉の鎖を外すと、扉に鼻をくっつけてきます。今日は噛みつき小僧じゃないといいなぁ、と思いながら無口を近づけると、当然のように無口にぱくっ。はいはい、そうですかい。口から無口を外させて、輪っかのところを鼻に通し、装着したつもりが、いつのまにかまた無口に噛みついていたアル。あごにかかるはずの部分が、口の中に入ってハミみたいになっていました。もういちど外して、今度は引き手をまるめたものを噛ませ、そのスキに強引に無口装着。引き手をつけて馬房から連れ出します。 アルフォンスの馬房から馬繋場までは、常歩でほんの10完歩もない程度なのですが、どうしても途中で止まりたくなるのが彼のクセ。今日も、馬繋場まであと3歩というところでびたっと止まり、押しても引いても動きません。仕方ないので振りかえってお尻をたたこうと思ったのですが、アルが横目で私を見ている。これは噛みつく隙をうがかってる目だなー、こいつめ。隙を見せると手首を噛まれそうだったので(実際、口元は私に向かって動いていたから)、振りかえることもままならない。困ったなー、と人馬ともに膠着していると、「いやー、見るにみかねて来ちゃいました」とK野さんの声。クラブハウスで休憩していたはずだったけど、切り上げて来てくれたみたい。K野さんが来ると、大して引っ張らなくても急に動き出すアル、あんた裏表ありすぎだっちゅーの。 馬繋場につなぎ、腰が引けながら馬着を脱がせます。見ていたK野さんが、「毅然とした態度をとれば大丈夫なんですよ」と言ってくれますが、だって噛まれるのイヤなんだもん。でもそこにK野さんがいるので、積極的に噛みにこようとはしないから、少しは安心して金具を外し、馬着を脱がせました。 蹄の裏堀りをする間も、しきりに振り向くアルフォンス。噛みつきたいというよりは、虫が気になるんだな。この季節になると、口は少しおとなしくなるのですが、虫をはらおうとして後肢が飛んでくるので、それも気を付けながらブラシかけ。 タオルと毛布、ジェルパッドを乗せてから鞍を取りに行きます。今までと鞍が変わっていて、ずいぶん軽いなこの鞍。その鞍を乗せていると、スタッフのK村さんが腹帯を何本も持ってやってきて、「どれが合うかな」と言います。あれ? そう言えばこの鞍、腹帯が着いてなかったんだ。「ずいぶん軽いなーと思ったら、腹帯がなかったんだね」「いや、それでも軽いことは軽いんだよ、その鞍」長さの合う腹帯を締めます。締めてみると、なんか鞍が後ろのほうにあるなぁ。毛布を乗せる段階ではかなり前のほうに乗せたつもりなんだけど、と思ってよく見ると、毛布が後ろにずれています。あー、やったな。背中に毛布を乗せると「じゃまだー」と思うのか、アルは肩をぶるぶるさせて後ろにずらしてしまう子なのです。腹帯を外して、再度鞍を着けなおします。 時計を見ると、レッスン開始5分前。ほかの馬ならまだ早いけど、アルフォンスの最大の難関であるハミかけに何分かかるか分からないから、始めてしまおう。頭絡の準備をしてから無口を外すと、待ち構えていたように頭を高く上げてしまうアル。「くぉらっ」と、まだ完全に外していなかった無口の額革で鼻先をとらえ、下に引っ張ります。ふん、負けねーぞ。無口を外し、頭絡を近づけたところでまた頭を上げてしまうので、今度は頭絡の額革で同じように鼻面をガッと引っ張ります。あとはハミを口に入れるだけなんだけど、それが一番噛まれそうで怖いんだよねぇ。右手でアルの鼻をしっかりと押さえ(ている間にも頭を上げようとするので、右手で鼻面をひっぱたきながら)、左手の親指を口角に入れて手のひらでハミを入れると、あれ、入った? 頭を上げられないうちに急いで頭絡を引き上げ、額革を耳にかけてしまいます。うわー、ひとりでハミかけたよ。近くにK野さんやK村さんがいてプレッシャーをかけてくれているわけでもないのに、すごいじゃん自分。 そのまま馬場へ連れ出しますが、ちょっと誰かに自慢したいぞ。馬場への出口のところでK村さんが馬場をならしていたので、「K村さん、ハミ1人でかけたよー」と声をかけると「なにっ!? アルもとうとう夏バテか!!」失礼だなー、くそー(笑)。 馬場中央にアルフォンスを止めると、K野さんが踏み台を持ってきてくれたので騎乗。K野さんに鞭を入れてしまいそうになりながら腹帯を締め直してもらうと、K野さんが「ちょっと金具が」と、鐙革の金具をきちんと奥にしまってくれました。でもこの鞍は小あおりが小さめで、あんまりきちんと隠れない感じ。「痛かったら言ってくださいね、我慢して乗ったりしないで」と言ってK野さんが去った後、鐙の上に立ち上がってみたら、またこれはずいぶん長いじゃないか。立ち上がれるけど、立ち上がった状態で股と鞍の間は2センチあるかな?という感じ。でも立てないわけじゃないので、とりあえずこの長さで頑張ってみるか。 2鞍目の部班はモンブラン、リトル・フロスティ、ウィンダムとアルフォンスの4頭。これだと当然モンブランが先頭だな、あの子は前に他馬がいるとかかるから。予想通り、「モンブラン、ウィンダム、アルフォンス、フロスティの順で」蹄跡に出ます。 アルフォンスは今日も虫が気になって歩きたくないようで、ときどき後肢を蹴り上げながら歩いています。でもせっかくハミ受けを知っている馬に当たったのだから、今回もハミ受けの練習するもんね。まずハミを受けさせる前に、前に出そうと思ってどんどん拍車を使います。先頭のモンブランもあまり行く気がないようで、前がつっかえていてウィンダムに追いつきそうになるので、できるだけ隅角を大きめに回りながら。 「手綱ちゃんと持って、速歩しますよー」じゃあ歩度をつめておかなければ。「はやあーし」で、ちゃんと速歩発進できたので、全くやる気がないわけではないようです。軽速歩をとって走り出してみると、別に立ち上がれなくはないんだけど、ぜんぜんかかとが下がらない。かかとが下がらないってことは鐙の上でのバランスがとりにくいので、ちょっと馬がつまづいたりしただけで上体を前に持って行かれてしまいます。速歩やるには楽なんだけどな。 アルも調子が上がってきたようなので、ハミ受け練習開始。しばらく馬の前肢の動きに合わせて、拳を交互に握ります。「ジャブしない、自分から譲っちゃダメですよ」左右に拳を握るときに、引いてからまた前に戻しているようなことを言われているらしい。そうか、譲ってるのか、私。譲らないで手綱を持つって、けっこう指の間が痛いし、腕の筋肉もかなり使ってる。こんなに力入ってていいんだろうか。 ずーっとそれを続けていると、ふーっとアルフォンスの頭が下がっていきました。おお!「そう、そう、譲らないでもっと我慢して」と言われているそばから、アルが虫を気にして首を振り、また頭を上げてしまいました。せっかくの屈撓が台なし。またやりなおしだぁ。 「馬の頭が下がった方が、馬も人も楽なんだから、『ここが楽なんだよ』って馬に教えてあげるんですよ」そう言われてハミ受けを続けます。頭を下げさせようと思ったら当然拳は下に下がるし、「拳もっと広げて」と言われ、両方の拳の位置が馬の肩より外になって、ほんとにいいのかこの位置って感じになってしまうけど、できるようになるまでは仕方ないんだろう。つい口でも、「下げて、下げて」と言ってリズムをとりながら拳を握ります。本当は「頭を下げる」ではなく、「馬を丸くする」というのが屈撓だと思うんだけど、それができるようになる第一段階はやっぱり頭を下げさせることなんだろうと思います。 それからも、少し頭を下げさせることができてはまた首を振られて台なし、の繰り返しでしたが、「ハミ受けを知ってる馬のときは、できるだけハミ受けをさせてあげるから」おお、K野さんの頼もしいお言葉。 フロスティが蹄跡に残り、ほかの3頭は馬場内側へ。「フロスティ、反対駈歩で」うわー、さすが上級者のIさんは言われることが違う。「内方引いて、外方入れればいいんですから、同じですよ」って、そりゃ理論では分かっても、反対駈歩を「される」のと「させる」のは違う。1度は失敗しながらも、Iさんはさすがにすぐ反対駈歩をこなしていました。その間に、私は鐙を1穴短くすることにします。この長さじゃ、確実に外方の鐙が外れる。鐙を直す私を見て、「金具当たりますか?」と気を遣うK野さん、「いや、そうじゃなくて、さすがにちょっと鐙が長くて、もう挫折したいの」。 他の2頭はまだあまり駈歩をやっていない方のようで、次は私の番になりました。とりあえず左手前で、アルフォンスを蹄跡に出します。「蹄跡から駈歩」の指示で、アルに内方の拍車をぐりぐり入れましたが、速歩が出てしまいます。あれ、アルって駈歩の扶助には素直な馬なんだけどな。ふたたび駈歩の合図をすると、1歩目だけはどうにか駈歩が出るのですが、もう2歩目に行く前の後肢が速歩に落ちている。なーんか、とりあえず駈歩っていうからやるけど、続けなくてもいいでしょー、って感じ。速歩のまま2〜3歩行かせて止めると、「すぐ止めて。止められないから、馬がそれでいいやって思っちゃってるんですよ。駈歩出ないなら鞭入れて」鞭を内方に持って、腹にぴしっと1度。「もう1回」もう1度ぴしっ。それから駈歩発進をしたのですが、今度も2歩か3歩で速歩に落ちてしまいました。もー腹立った。止めて手綱を強めに持ち、腹にかなり強めの鞭を2度続けて入れます。さすがにちょっとびくっと首を上げたアルフォンス。次の駈歩発進では素直に駈歩が出て、しかも続くじゃないの。やっぱりあんたサボってたのね。 でも左手前での鏡前の隅角を曲がりきれず、速歩に落ちてしまいました。基本的にやる気がないんだな、今日は。 常歩に落としたところで、もう時間が迫ってきたので、他の馬たちが蹄跡に戻されてきました。これで沈静化と思ったら、「アルフォンス、ウィンダムのところまで駈歩」じゃあこれで最後だから、頑張ろう。駈歩の扶助を送ると、発進はわりとすぐできたのですが、半周も続けることができませんでした。頑張って拍車使ったんだけど、2鞍目だと、私もちょっと脚が弱くなってるのかしらん。 そのまま手綱を伸ばして、常歩で沈静化します。 さっきロゼッタでやったように、前肢と後肢の動きの関連を感じようと思ったのですが、常歩だと反動のすくないアルフォンスでは、後肢の揺れがあまり感じられないので、これはちょっと難しそうだな。ロゼッタのときにしよう。 馬場中央に馬を並べて挨拶し、下馬。アルフォンスは今日はこれでお仕事が終わりなので、馬繋場に上げて手入れをします。 馬装を解除して、蹄の裏堀りをして肢を洗っていると、K村さんがバケツに消毒液を準備してくれました、皮膚の弱いアルフォンスは、これで全身を拭き洗いするのです。 バイトスタッフの高校生、UくんとOくんが手伝いに来てくれました。Oくんは最近来はじめたばかりなので、Uくんに習いながらバケツの液にタオルをひたし、アルの身体を拭いてくれます。私も自分の乗った馬なので、タオルを持ってきてアルの身体を洗うことにしました。周りから「おお、3人がかり〜。贅沢だなアル」と冷やかされ、K野さんに至っては「3人でやっと1人前ですねぇ。いや、1人前まで行ってないかも」と言う始末。ふーんだ。 「お尻もちゃんと洗えよ、後ろから手突っ込んで。横からやると蹴られるから、後ろからな」とK村さんに言われている高校生2人組、ついにK野さんに「違うよ、こうするの」と手を出されてしまいました。見ていると、私も今まで馬のお尻を洗うのは少し遠慮がちにやっていたのですが、全然遠慮しなくていいんだな。 バケツの消毒液は、タオルをひたして絞らずに、馬体に浴びせるようにして使います。タオルをびっちょりにして、できるだけ消毒液をこぼさないうちにアルの背中の真中に投げるようにして置き、そこから下へ拭き下ろしてやろうと思うと、アルがヘンに腰をくねらせて、私にお尻を向けてきます。「お尻洗ってって言ってるんだよ」とK村さん。うひゃひゃ、かわいー。しっぽを持ち上げて、「ここもね」とK村さんのアドバイスを受けながらお尻の間をタオルでこすってやると、アルがすっごいだらしない顔になってて、気持ちいいらしい。いやー、夏の手入れは楽しい。 K村さんに連れられて馬房に帰るアルフォンスを見送ってから、クラブハウスへ引き上げます。長靴を脱ぐとき、えらく左膝の内側が痛いので、ついでにキュロットをたくしあげて見てみたら、「あー、皮むけちゃった」。みみず腫れのようにすりむけていました。なんか革長のへりとキュロットの膝革が当たるなー、とは思っていたけど。それを聞きつけたK野さんが「どこかケガしました?」と聞いてきたので、「ほら、これ」と見せると、「あーあ、膝で締めて乗るから」。う、まぁ確かにそうなのだが。でもそのあと、言い過ぎたと思ったのか「革長当たってたんですか?」とフォローを入れようとするところが、彼のいいところだったりします。 でも2年ちょっと乗馬やってて、すれて皮がむけたのは始めてでした。お風呂が痛かったよぅ…。 |
|
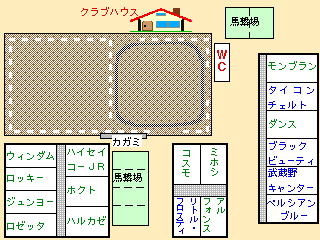 ↑日の出乗馬倶楽部の見取り図 (緑字:貸与馬、青字:自馬) |
||
| ←126鞍目 | 128鞍目→ |