| ←156鞍目 | 157鞍目・なみあし、はやあし、かけあし (2003.12.6 あきる野・日の出乗馬倶楽部) |
158鞍目→ |
|---|---|---|
 この日2回目の経路。 斜めに手前を換え、線上中間速歩を軽速歩で。 |
12月20日の試合に向けて、今日も1課目の練習。また今日も微妙な天気で、昼間に雨が降る予報になっていましたが、午前中はなんとか保つだろう。9時の予約なので、8時過ぎには倶楽部に到着しました。今日からは新しい先生たちが教えてくれることになっています。 馬場には早くも、馬場標識が置いてありました。クラブハウスからママさんが出てきて、「先生方もとってもやる気なのよ、今から下乗りをしてくれるから」今日の指導はN子先生(馬場専門)ですが、最初にちょっとO先生(障害と馬場)が乗ってくれて、そのあとN子先生も乗ってくれるということです。馬繋場のほうを見ると、さっそくロゼッタの馬装をしてくれている様子。 クラブハウス横で、1課目の経路表を確認しているN子先生に挨拶すると「あなた経路は大丈夫だよね?」「まぁ、何度か踏んでますから」「良かったー、じゃあ大丈夫ね。1課目なんてはるか昔のことだから忘れちゃったよー」ってN子先生、意外と無邪気です…。 先生たちが下乗りをしてくれている間、自分は着替えをしてストレッチ。先週N子先生に教えてもらったばかりの股関節のストレッチ、これで少しでも鞍付きがよくなればいいんだけど。 O先生が下馬してから乗り替わったN子先生が、抑えた声ながら「あーニブい!」と言うのが聞こえてしまいました。確かに、ロゼって反応が1テンポ遅れる感じはあるんだよねぇ。時間が来たので、自分の踏み台を持って馬場に出ると、N子先生が「乗ったらすぐ動くようにしておいたから、最初は鞭もいらないかな」ということで、長鞭を預かってもらいました。で、これでフラットワークかなと思っていたら、「最初はまず常歩で、ひたすら経路踏んでみよう。速歩のところも駈歩のところも、ぜんぶ常歩で。ただし常歩でも、中間速歩とか駈歩のところは歩度を伸ばしてみて」うわー、私常歩で歩度伸ばすの、すっごくヘタクソなんですけど。 とにかくいったん入場点(A点)に向かい、馬を返してX点へ。X点で停止すると、さっそく指導が入りました。「停止は、自分の体がX点に来たときに止まるの。B点とE点横目で見て、そこまで来て止まるようにね」そ、そういえばそうだったかも。標識通過は、つい馬の鼻をポイントにして考えてしまっていたんですが(それは競馬…)、自分の体だって聞いたことがあるようなないような。「斜めに手前を換えとか、駈歩発進も自分の体が目安ですか?」「そう、ポイントは全部自分の体が通過するとき」なるほど。今回は常歩でじっくり踏めるんだから、そこに気をつけて回ってくることにしよう。ここですでに重そうに見えたのか、「やっぱり鞭は持とう。使わなくても、持ってるだけで違うはずだから」と、長鞭を返してくれました。 さて、常歩だからできることをしよう。隅角もできるだけ奥まで踏み込んで、きっちり回す。「そうそう、隅角だいじにね」。E点を自分の体が通過してから左に回転、あれ、B点が思ったより左にある。行き過ぎちゃったかしら。「ちょっとB点ずれてるから、今のあなたが正しい。そのまままっすぐね」と、ほとんど一緒に歩きながら教えてくれるN子先生。小柄な体で、この砂の深い馬場を歩くのはけっこう辛いだろうに(経験済み)。 常歩のまま経路を回り、A点から輪乗り。「そこはね、もっと大きくていい。ほら、ここ(K点)が6mで、ここ(V点)があと12mでしょ、そしたらここまで来てやっと20mだよ」と、先生は自分の足で歩いて場所を指示してくれます。ふたたびA点へ戻り蹄跡へ。「ほら、そこは本当は駈歩だから、常歩の歩度伸ばして。気持ちだけ駈歩」あー、なかなか伸びない。C点まで行ってすこし歩度をつめ、斜め手前変換。ここも「中間速歩だから、歩度伸ばさなきゃ」。A点から輪乗り、戻ってきて、ここから駈歩のはずだから、鞭を使って歩度を伸ばす、と。右手前よりは少し伸びたけど。 蹄跡で、常歩だからせめて隅角は深く回って、E点から左に回転、X点へ。「ちゃんと左右見てね、自分が標識の間に来たと思ったら止めるんだよ、あー早い早いっ」横目で左右を見ながら、でも頭は動かさないようにして、停止。 「じゃあ次は、最初から最後までずっと速歩でやってみようね。今のと同じで、中間速歩とか軽速歩のところは歩度を伸ばすようにしてみて」へぇ、面白い。それは面白そうだ。 A点へ向かおうとすると、「その辺りで速歩で輪乗りとかしてみて、いいと思ったら合図して入ってきて」ということで、A点からX点の間くらいで軽くフラットワーク。あーあ、速歩すら出ないよ。仕方ないので拍車で蹴って、速歩。せっかく輪乗りで動いてみるように言われているんだから、内方脚で外に出して、外方で受けてというのをしっかりやるようにします。ロゼも内方姿勢をとってくれるようになってきたみたいだし、ほんとはもっと前進気勢を作りたいけど、ここいらで経路に入ることにしよう。 「入ります」と先生に声をかけて、A点からX点へ。X点で停止、敬礼すると、C点の外にいたO先生が答礼してくれました。そこから速歩発進、C点から蹄跡へ。隅角でできるだけまっすぐ行かせ、深く切れ込んでから方向転換。でもこうすると、外方で曲げていると間に合わなくなって、内方の開き手綱で曲げるようになってしまうな。 速歩で蹄跡を踏み、V点から中間速歩で斜めに手前を換え。そこから歩度を伸ばすために、その前の短蹄跡はできるだけ歩度をつめていこう。頑張って脚を使いながら歩度をつめ、V点から拳を緩めて同時に鞭を入れると、すっと歩度が伸びました。自分としてはもう少し勢いが欲しいと思ったのですが、N子先生が「そうそう、うまいうまい」とほめてくれたので、これでいいことにしよう。蹄跡に入るちょっと前から歩度をつめ始め、蹄跡では歩度をつめます。 馬場の外からO先生が、「隅角や方向転換のときが止まりそうになるみたいだから、そこで注意して前に出すようにしてください」とアドバイスをくれました。なるほどね、と次の隅角では軽く鞭を使いながら回ります。もう1度斜めに手前を換え、ここは本当は自由常歩だから歩度をつめて、蹄跡から少し歩度を伸ばしていきます。 速歩のままA点から輪乗り。今度はさっき言われた大きさで円が描けるように、頭の中であらかじめ円を描いてから踏むようにします。もとのA点に戻って、ここから駈歩だから歩度を伸ばして、と。「人も馬も駈歩のつもりでねー」長蹄跡で歩度を伸ばし、C点で本当は下方移行なので歩度をつめます。 斜めに手前を換え、左手前でA点から輪乗り。もとのA点に戻って、さっきと同じように歩度を伸ばしながら長蹄跡を速歩しますが、最初の斜め手前変換ほど歩度が伸びないな。つめてつめて伸ばすのはそんなに難しくないけど、伸ばしてまた伸ばすのって難しいんだなぁ。 C点から歩度をつめ、E点まで。そこから輪乗りでX点〜G点直進。一応ちゃんと敬礼をすると、O先生がきちんと答礼してくれました。 「じゃあ、少しゆっくり歩いて。疲れたよね?」「はい、少し」「ちょっとリラックスしよう、人も馬も。馬上運動でもなんでもしていいから。それから本番のつもりでもう1回やろう」よーし。でもその前に、「上着脱いでいいですか?」「暑くなるよねー、どうぞどうぞ」朝方はかなり寒いと思っていましたが、常歩と速歩だけでもこんなに暑くなるか。来ていたトレーナーを馬上で脱ごうとすると、先生が鞭を預かってくれました。相方にトレーナーを渡して、手綱を持ちなおします。 「鞭を入れたら、拳を少し前に出すくらいで、両手一緒に少し前に出して。鞭入れて引っ張っちゃったら、『行け』って言って『行くな』ってやったら馬どうしていいか分かんないから、鞭を入れたら少し前に出してあげるの」 O先生からは、「自分が次にいくポイントを、ちゃんと先に見てくださいね」というアドバイス。そうか、馬場の経路踏むのも障害も、自分がちゃんと先を見て組み立てていくっていうところは同じなんだ。 A点付近で常歩、ついでに軽く馬上運動をして、肩を回したり股関節を回したりしてみます。「いいと思ったら合図してね」。右手前、左手前でそれぞれ速歩で動かして、それなりに前に出せるようになったと思ったので、「いきます」と合図。 A点に向かおうとすると、ぱたっと速歩が出なくなってしまいました。今までちゃんと走ってたくせに、ナメてもらったら困るな。鞭を入れてもなかなか速歩が出ませんでしたが、A点付近でようやく速歩になりました。そこからX点に向かって、速歩で入場。どうしてもここでよれてしまうロゼッタですが、O先生いわく、このA点からX点までがうまくできればその後の点数も良くなるのだそうだから、できるだけぴしっと乗るようにします。 X点、横目で標識を見ながら、自分の体と標識の位置があったところで停止、敬礼。速歩発進して、3回目の経路練習に入ります。 速歩で順調に回り、V〜X〜R点の斜め手前変換で歩度を伸ばすのも、けっこういい感じ。ところが次のC点、速歩から常歩に落とすのをまた忘れてしまいました。それに気がついたのはすでに隅角付近。先週K野さんには「経路違反にはならないけど、減点対象」と言われていたのにな。 あわてて常歩に落とし、S点からは手綱を伸ばして自由常歩。すこし手綱を伸ばして歩かせると、「思いっきり手綱を放しちゃっていいよ」と言われ、思い切って手綱のつなぎ目を片手で持つくらいにします。P点手前、「そこらへんから少しずつ手綱持つ準備して」手綱を持っていないほうの片手で徐々に手綱を絞っていき、P点からきちんと両手で持ち直しました。F点の先の隅角は砂が深くて、ロゼはなかなか隅角の奥まで行こうとしないのですが、そこは頑張って奥まで行かせてから方向転換。「そうそう、隅角いいよ」 続けてA点から速歩ですが、そのちょっと前から「次は速歩でしょ、その辺からもうちょっと前に出さないと」あぁ、常歩の歩度を伸ばしておかないといけなかったな、と思ったときにはもうA点。慌てて速歩発進しますが、ちょっとA点よりも先に行ってから速歩になりました。 速歩で輪乗り、大きさに気をつけてと。A点に戻ったところから駈歩発進…あらら、失敗した。勢いが足りなかったな。止めて駈歩発進しようかな、と思ったのですが「輪乗りからやり直し。大丈夫、絶対出せる」とN子先生に言われ、そのままA点に向かって輪乗り。「輪乗りから駈歩に入る前から、もう外方引いておいて、A点から鞭入れちゃって。大丈夫、この馬何やってもぶっ飛んでいかないから」はい、良く知ってます(笑)。 A点に戻ったところでもう一度駈歩発進、う、出ないかな? と思った次の瞬間、ちゃんと駈歩になりました。あーよかった。ただ隅角をかなり浅く回ってしまい、長蹄跡でも内に入ってきそうになったので、あわてて内方で壁を作りながら外に出します。するとけっこう素直に外に出たロゼ、今度は標識に近づきすぎて踏まんばかりの勢い。頭いいから踏んだりはしないだろうけど、パイロンの外に出たら経路違反だからね、出ないでよ。 C点で速歩に移行、常歩に落ちかけましたがどうにか速歩に戻します。斜め手前変換して、左手前でA点から輪乗り。今度こそA点から駈歩を出すぞ、と気合いを入れ、一瞬出そうになったのですが、やっぱり速歩でした(あとで相方が撮ってくれた動画を見ると、ここで私が引っ張りすぎて、ロゼがいったん出そうとした駈歩をやめてしまった感じ。悔しいなぁ)。 続けて駈歩を出そうとしたのですが、早い速歩になるばかりで、こうなったらどうやっても出ないだろう。いったん止めて常歩から駈歩発進。やっぱりこれなら出るのよね。すでにP点を過ぎてしまいましたが、そのままC点まで駈歩で蹄跡行進。C点で速歩に落とし、E点から半巻きしてX点通過、こら止まるんじゃない。G点の手前でカンペキに止まりそうになり、最後の2完歩くらいはほとんど常歩でしたが、どうにかG点で停止、敬礼。 馬を愛撫して手綱を伸ばすと、「ポイントポイントは、うまく回れてましたよ。駈歩だけうまく行けば、けっこういいと思います」とO先生。N子先生にしろO先生にしろ、褒めるのが上手いなぁ。ほんのちょっとでも良かったところを見つけて褒めてくれる、やる気にさせる指導って感じ。 常歩で沈静化していると、「自由常歩は、今のそれなんだよねぇ。馬も人もこれくらいリラックスしてるのがいいんだよ」とN子先生。わはは、確かに沈静化のときが一番力が抜けていて、馬の動きに逆らわないかも。 この日記を書いていて、ふとN子先生が何を教えたかったのか想像してみたんですが…。私が子供の頃、母が音楽の先生だったので、ずいぶんピアノのレッスンでしごかれたものですが、ピアノの発表会やコンクールの前によく言われました。「楽譜どおり弾いたって皆と一緒、それ以上の何かを出せ」と。音のふくらみだとか強弱、そういうもので表情を出して初めて「演奏」なのだと。それと同じことで、決められたコースをただ踏んでいるだけでは馬場馬術じゃない、自分なりのメリハリをつけてこそ馬術なんじゃないだろうか。そういうことを教えてくれたかったのじゃないかと、思った次第です。深読みかもしれないけどね。 |
|
 3回目。自分で言うのも何だが、 だいぶ肩のあたりの窮屈さが抜けたかな |
||
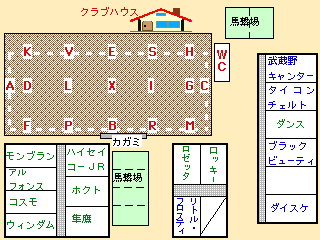 ↑日の出乗馬倶楽部の見取り図 (緑字:貸与馬、青字:自馬) |
||
| ←156鞍目 | 158鞍目→ |