| ←157鞍目 | 158鞍目・敬礼からやり直し (2003.12.13 あきる野・日の出乗馬倶楽部) |
159鞍目→ |
|---|---|---|
|
今日も朝イチの時間で1課目の練習。とても寒かったけど天気は良さそうで、8時過ぎに武蔵増戸に到着。駅から降りて日陰の道に入ると、道ばたの草が白く見えます。あぁ、このへんってもう霜が降りるんだ。…待てよ、ってことは日の出の馬場もけっこう日陰だから、凍ってるんじゃないのかぁ? いやぁ〜な予感を抱えつつ日の出まで歩くと、途中の山田大橋で少し足が滑りました。うぇ、路面が凍ってるぅ。 転ばないように気をつけながら日の出に到着。ば、馬場が白い…。O先生がいたので「もしかして馬場、凍ってます?」と聞くと「凍っちゃってますねぇ。今オーナーにお願いしてハローかけますんで、少しお待ちください」という返事。トイレに行く途中でN子先生に会うと、「今ハローかけてもらったら下乗りするから、ちょっと待っててねー。私さっき、何も考えないで馬場に入ったら転んじゃったのよー」冬の日の出の風物詩と言えなくもないですが…。 着替えをしますが、うっ、革長がつめたくて固い。「中であったまってねー」というママさんの勧めで、拍車はクラブハウスの中で着けます。オーナーがハローがけをしてくれて、N子先生がロゼッタの下乗りをはじめました。 クラブハウスの外に出て、馬場でN子先生が乗るのを見ながら待機していると、N子先生が馬上から「KYOKOさーん、今日は上着もトレーナーもなしだよー」「な、なしですか?」えーと、先週途中で暑くなってトレーナー脱いじゃったしな、それでかな。カットソーだけじゃ今は寒いけど、あとで暑くなるだろう(あとでN子先生に言われたところによると、暑い寒いの問題じゃなくて「トレーナーなんか着てると背中の形が見えないのよ、一番大事なところなのに」ということ。乗馬用の、体のラインにぴったりしたベストなんかならOKなのだそうです)。 そうは言っても、乗る直前と乗った後は寒いだろうから、ライディングジャケットを馬繋場に置いておくことにしました。 「私が乗ってる間でも、標識作っちゃっていいから」とN子先生がO先生に言っていて、O先生がポイントごとにパイロンを設置し始めました。ヒマだし、せめて自分で標識くらい置くかな、と思って、O先生に標識のしまい場所を尋ねると、場所を教えてくれたついでにO先生が言うことには「今日の馬場は10%くらい縮小版で作ってあるの、分かりますよね? 正確に計るとここ、60mとれないんで、57mくらいらしいんですよ。実際によその馬場に出てみると、だいぶ広く感じるかもしれませんが、でも縮尺は同じですから、そう戸惑うことはないと思いますよ」。ついでに「ポイントに入るときですけど、馬の鼻を隅角に突っ込ませるくらいの気持ちでいいですよ。馬の肩と自分の肩を、標識に触れさせるくらいのつもりで。僕もそうやったときのほうが、点数稼げました」と、O先生の教えてくれることは几帳面かつ実戦的です。 標識を持ち出して、O先生の置いてくれたパイロンに標識を並べていきます。あらかじめ順番通りに重ねてあるそうなので、そのまま並べていけば合うようになっているはずですが、ちょっとドキドキ。だって自分でカンペキに覚えてるの、ACEBXくらいだし(あとで乗馬日記書くときには、経路表見ながら書いてます)。でもあとから見たら、ちゃんと合ってました。ほっ。 標識を並べ終わって、N子先生の下乗りも終わったようなので馬場の中へ。「踏み台いる?」「あー、欲しいですけど、足上げしてもらえれば」「じゃあ足上げで乗ろう」と、N子先生に足上げしてもらってロゼに騎乗。「じゃあまず常歩で、一度経路を回ってみて」あ、先週と同じだな。 指示どおり常歩でA点から入り、X点で停止、敬礼。するとN子先生が「Mさん(一緒の試合で3課目を踏む予定)にも言ったんだけどさ、敬礼は慌ててしなくてもいいんだよ。いい、まず止まるでしょ。そしたら手綱と鞭を片手にまとめるよね。そこから、こう手を下に出したら、手の甲を審査員に向けて返すの、これが敬礼。男の人だったらメットをとって、メットのてっぺんを審査員に向けるでしょ。女はメットを脱がないけど、それと同じことをやるんだよ」えっ、そうだったの!? 何度か試合に出てるのに、そんなの知らなかったよぅ。ただ手を下に向けて出せばいいんだと思ってた。「それで審査員が帽子をとって答礼するなり、会釈するなりするでしょ。それから審査員が椅子に座ったら、やっと演技をはじめればいいの。その間も馬に緊張感を持たせるために、脚はちゃんと使うんだよ」その通りにして、常歩でC点へ向かう私に、「そのときに審査員に向かって笑う余裕があったらなおいいね」だそうです。 先週と同じく、常歩のまま1課目の経路を踏みます。当然先週と同じように、中間速歩や駈歩のところは歩度を伸ばして…と思うのですが、今日のロゼッタはまたずいぶん重いな。おかげで隅角やポイントはきっちり回れるけど、前に出ろっての。しかもよれるし。 回転や方向転換のポイントでは、さっきO先生に言われたように自分の肩を標識に近づけるつもりで歩きます。「そうそう、隅角大事にね。1課目までは開き手綱使っていいんだから、思いっきり奥まで行かせてから曲げて」ってことは、2課目より上では開き手綱は正しい扶助とは認めてもらえないってことだよね。できるかぎりは、外方で曲げるのが正しいんだろう。 自由常歩で斜め手前変換、手綱を最大にゆるめてしまうと、まーよれることよれること。「人間が真っ直ぐ向いてないと」そうなんですよねぇ。拍車や鞭を使うときに僅かにバランスを崩してしまってるんだろうけど、それにしても今日は派手によれる。 ずっとついて歩きながら細かく指導してくれるN子先生、「鞭の使い方はね、このくらい手首を返しちゃっていいんだよ。ピシッてこうやって、拳の内側が上に向くくらい。ちょっとやってみな」どうせロゼッタだから、鞭を入れたところで鋭い反応はしないだろうから、言われたとおりに拳を返して、鋭く鞭を使ってみます。でもほんの2〜3歩しか反応しないし。「ほんと重いよねーこの馬、人間がついて歩けるなんてどうかしてるよ」こんなに拍車も鞭も使ってるのに、ねぇ。こんなことじゃいけないのはわかってるんですが。 A点から輪乗り、「輪乗りは蹄跡に必ず3点触れるようにね、そうでないと輪乗りと認めてもらえないよ。でも蹄跡を歩いちゃダメだよ」A点に戻り、そこから本当は駈歩だから歩度を伸ばしたいのに、鞭を入れた時しか歩度が伸びない。「鞭を入れたら手綱引かないで、そうそう、そうだ」 蹄跡行進から斜めに手前を換え、「そこは中間速歩だよね。お尻が跳ねても鐙が外れてもいいから、とにかく体を起こして自分が馬を前に出してるんだってアピールするんだよ」 ふたたびA点から輪乗り、駈歩のつもりで蹄跡行進。E点で方向転換、半巻きでX点へ。先週言われたように、自分の行く先のポイントに目を向けながら巻き乗り。そこでN子先生が、「もうちょっと大きく膨らむといいね」と、私とロゼが歩いた蹄跡を示し、「もうちょっとこのくらい」と、足で正しい蹄跡を作ります。確かに私の作った蹄跡は、X点に来てあわてて曲がりましたというような、ひしゃげた山形をしています。そこからG点まで歩き、さっき教えられたとおりに敬礼をして経路終了。 「次はじゃあ、自分の思うとおりにやってみな」「えーと、駈歩なしでですか?」先週は、常歩だけの次は速歩だけで回ったので。「ううん、本番どおりでいいよ。A点のあたりで輪乗りして、自分がいいと思ったら合図して」 「今日はマルタンつけてないからね、それに頼らないでやってみな」えっ? あら、ほんとだ。一応装着されてはいるものの、ハミを通さないで首の上でつないであるだけでした。道理でよれるわけだ、気がつかなかった。 A点に向かい、速歩でロゼを動かしますが、一応動くんだけど重い重い。せっかく先生が下乗りしてくれたのに、経路1回分まるまる常歩したので伸びきってしまったみたい(ほんとーは伸びないように歩かせなきゃ、ってのはこの際置いておく)。駈歩でエンジンかけたほうが早いかなー、と思って常歩から駈歩発進しようとしますが、常歩の歩度が伸びるだけで速歩にすらならない。うぅーむ。調子いいときだと、外方脚引いただけで出るのにな。 いつまでもパタパタしていても仕方ないので、ある程度速歩で歩度が伸びたところで経路に入ることにしました。「入りまーす」と先生たちに合図して、速歩でA点へ。 A点からX点まで、できるだけ真っ直ぐ速歩で行きたいんだけど、あーよれてるよれてる。どうにかこうにかX点まで持っていき停止、C点の向こうにいるO先生とN子先生に向かって敬礼。ロゼが首を下ろそうとしたので脚で起こして、さっき言われたように手の甲を返して先生に見せると、O先生が帽子をとって答礼してくれました。ここで慌てず、だな。手綱を持ちなおして、速歩発進。 ほとんど常歩のような速歩でしたが、一応速歩で出られたので、そのままC点から左に回転、蹄跡へ。最初の隅角で、予想外に「そうそう、うまい」と言ってもらえたので、次の方向転換ではもっと頑張っちゃったりして。 V〜X〜R点の中間速歩、ここで歩度を伸ばすために、その前からつめておきたいところですが、つめるためには馬の勢いが足りない。脚でむぎゅーっと締めても足りないので鞭を使い、拳で詰めてからV点で方向転換、これは自分では行き過ぎたか? と思うくらいまで標識に接近し、自分と馬の肩を標識にぶつけるつもりで、と。方向転換の直後に拳を許し、ついでに鞭を1発くれてやると、なんとか歩度が伸びました。自分ではもうちょっとだな、と思ったのですが、「そうそう! そうやって歩度を伸ばしてることをアピールするの!」あ、これでアピールできてるんだ。 蹄跡に入って、次の斜め手前変換は自由常歩だから…と考えているうちに、常歩に移行するべきC点を速歩のまま通り過ぎてしまいました。うわー、先週も同じ失敗したのに! O先生に、「早めに出すのはOKだけど、標識を過ぎちゃうのは『馬をコントロールできていない』と見なされるからダメ」と言われていたのにな。 自由常歩でよれによれるロゼッタをなんとか歩かせ、P点に近づいたころに手綱をまとめ、持ち直します。A点から速歩…ああぁ、常歩のまま標識過ぎちゃった。うーん、もっと前から元気良く歩かせてないといけなかったんだな。拍車を入れて速歩を出させ、20mの輪乗り。A点から駈歩発進、あーこれも出ない。なんとか出ないか、と思ってK点くらいまでは頑張ったのですが、N子先生に「輪乗りからやり直して」と言われてしまいました。そのまま輪乗りに戻って、「少し前からもう外方引いちゃって、鞭でも何でもいいからとにかく出せ! 出せる!」ふたたびA点から駈歩発進。A点はすこし超えてしまったけど、ようやく駈歩が出ました。フラットワークから重かったもんなぁ。 駈歩で蹄跡行進、C点で速歩に落とすところまでは難なく行きました。ちょっと思ったより馬なりか? っていうか私、手綱緩いかな? ロゼってハミをかっちり当ててやったほうが駈歩出やすいんじゃなかったっけ。 R点から中間速歩、「そうだ、体起こして!」さきに言われていたとおりにやったら、本当に鐙が外れてしまった。でもとにかく体は起こして、V点まで。駈歩の後だからロゼもやる気になっているようで、ちゃんと歩度が伸びています。 V点で蹄跡に入り、ここの隅角はキッチリと。A点に行くまでの間に鐙をはき直し、A点から輪乗り。ふたたびA点に戻ったところから駈歩発進。一瞬出そうになったのですが、あっハミ引っ張っちゃった! 当然ロゼは駈歩に移行するのをやめてしまい、速歩ですたたたたーと前に出てしまいます。P点くらいまではそのまま駈歩に移行できないかと頑張ってみたのですが、ダメそうだったので、いったん止めて常歩から発進することにしました。…あれ、止められないぞ。ロゼにしてはやる気になっていたのか、私が半減却のつもりで使った脚が前に出す脚だったのか(たぶん後者)、速歩でけっこう体を起こして手綱を引っ張っているのになかなか止まらない。B点を過ぎてやっと常歩に落とし、駈歩発進。「そう、諦めないで!」常歩に落とすと簡単に出せるんですよねぇ、これが。C点まで駈歩、そこから速歩に落とします。 E点まで速歩、ここからX点までは、さっきN子先生に言われた蹄跡をあらかじめ頭の中で描いて、その上を走るように半巻き。X点からG点まで、よれないようによれないように。I点すぎるまではけっこう悪くなかったのですが、私が横目で標識を見たとたん「終わりでしょ?」とロゼが常歩に落ちようとしました。「あと少しあと少し!」というN子先生の叱咤をよそに、止まる気まんまんのロゼ。最後の2完歩はまったくの常歩でしたが、ようやくG点まで連れて行って停止、敬礼。うはぁ〜。 レッスン終了時間まではもう少しありましたが、「自分で好きな動きをしていてもいいし、沈静化を兼ねて常歩で動いててもいいし」とN子先生に言われたので、後者を選択。常歩で馬の動きを感じることに努めることにしました。 歩いているとN子先生に「どう、マルタンなしだと?」と聞かれたので、「よれますねー!」「そう、それがその馬の本当の動きだよ。それを人が修正して真っ直ぐ乗らなきゃいけないんだけど、道具に頼ってるとやらないでしょ。馬もそれに頼って、サボるようになるから。ハミが常にかかってて遊びがない状態になるから、ハミに乗っかってサボるんだよね、そうすると楽だから」。ああ、その状態にはものすごく心当たりが! 「やりますやります、この子。ちょっと油断すると首下げてサボってる」「そうだよね。あの馬、別に頭うるさくないでしょ? マルタン必要ないよ」ということでした。 「試合ではこんな重い馬出てこないと思うから、もうちょっと出せるはずだよ」だそうです。うーん、出る馬を抑えなれてないから、それはそれで大変かも。 |
||
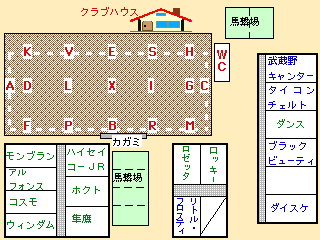 ↑日の出乗馬倶楽部の見取り図 (緑字:貸与馬、青字:自馬) |
||
| ←157鞍目 | 159鞍目→ |