| ←116鞍目 | 試合・万年4位は返上 (2003.4.13 山梨・八ヶ岳乗馬会 ララミー牧場) |
117鞍目→ |
|---|---|---|
|
折り返し手綱をとめてもらっているところ。助かった   この馬の首の下がりよう、まるで上手い人みたい(笑) 隅角の手前なので、押し手綱で外に出そうとしています |
試合前日の17時すぎ、I野先生のお車で日の出乗馬倶楽部を出発。そのころ、先発メンバーはとっくに宿泊先のペンションに到着していましたが、途中で夕食を摂ったりしてゆっくり行った私達が到着したのは22時。 お風呂をすませて、それから24時くらいまで、先生を交えてみんなでおしゃべりをしていましたが、そのとき先生が私におっしゃるには「今日のレッスン見たけど、どうしても左の脚が固いんだな。右の脚はいいんだけど、左の脚が引けなくて突っ張っちゃってるんだよ。ふだんから、ちょっと引きすぎってくらい引いててちょうどいいかも知れないな。それだけ気をつけてれば、明日はいいセンいくぞ」あー、左足ね。そっちの足は、成長期に靭帯をやっているので、右足よりもちょっと不器用なはず。 さらに、いいセン行った暁には、「夏にはまたここに来て、今度は3級検定を受けるように」とのお達し。「大丈夫、今日の駈歩ならいけるよ」ということですが…。 5時半、起床。ちょっと階下が騒がしくて眠れず、あまりコンディションは良くないけど、無理矢理起き出して身支度。朝食をいただき(白キュロの腰回りがきつくて、半分しか食べられず…)、I野先生の車でララミー牧場へ。 7時半、ララミー牧場にみんなが集合しました。今日の選手団は12人、出場はしないけど応援に来てくれている人もいます。みんなを集めて、試合前のミーティング。お互いに馬付をして助け合うように、などの注意事項を言われます。 「ほか何かないか? 昨年の選手からは? 」昨年も出場しているのは、私を含めて4名しかいないので、私が「競技上の注意事項は? 巻き乗りですとか」と進言すると、「そうだな。日の出では『各個に巻き乗り』『順次巻き乗り』って、ちゃんと言ってくれるけど、ここでは『巻き乗り』としか言ってくれないかもしれないから、ただの『巻き乗り』なら、各個に巻き乗りのことだからな。あとはそうだなぁ、去年のことだが」ここで、先生の冗談めかした口調と視線で、私の去年の失敗談をするのだと分かってしまいました。 「斜めに手前を変えようとして、斜線上で馬を真っ直ぐ行かせようとしたら、そのまま馬が勝手に反対方向に曲がっちゃった人がいるんだよな」「先生、もう許して」と思わず自白。「先輩の失敗に学んで、みなさんはそういうことのないように」失敗談だけ先輩でもしょうがないんだが。 8時すぎ、クラブハウス前で開会式。ララミー牧場主催の運動会と、社馬連グリーンカップが共催なのは昨年と同じですが、今年は社馬連と、ララミーや他の乗馬クラブ(一般と総称)でグループを分けることになったようです。 さっそく第一競技の部班競技の抽選がありました。速歩部班の私が引いたのは、2班の2番騎、馬名はシルバーウィング。3グループのうち、1班目は社馬連、2.3班が一般となっているので、日の出のメンバーはみな2班か3班。 馬があらかた決まってから、今日は日の出で留守番をしているK野さんに電話。彼はララミー牧場で修行をしていて馬を知っているので、教えてもらう約束をとりつけていました。でもシルバーウィングのことは、「よく知らないですね」ということ。ちぇっ。「でも拍車と鞭は、とりあえず必須で。いらなきゃ外せって言われますから」。昨日のレッスンのとき、拍車が使いにくかったのはきちんと足についてなかったからだなー、と思い、拍車につけているアーム(ゴムのすべり止め)を外し、拍車を曲げて幅を狭くして、きついくらいに足にセットします。 1班目の競技が始まるので、試合場になる覆い馬場へ、みんなで馬を見に行きます。前の班の人が乗ってる様子を見て、自分の馬のことを少しでも知りたい。 シルバーウィングってなくらいだから、芦毛に違いない。いたいた、2番手にいる白い馬、割と大きめだな。審査員が馬名と選手名を読み上げるのを聞いて、それが自分の乗る子だと確認できました。 競技がはじまり、馬場の囲いにへばりつきで見ていると、自分の目の前を馬が通りすぎていきます。よく見ると、シルバーウィングには折り返し手綱がついている様子。馬の頭を下げさせるためにつけるものですが、日の出ではコスモくらいしか折り返しを使用しないので、使い方がわかりません。 あわててI野先生に「先生、私あの芦毛に乗るんですけど、折り返し分かりません」と聞きにいくと、「手綱とおんなじだよ。持ち方は分かるな? 」今ウィングに乗っている人を観察すると、手綱は定石どおり薬指と小指の間に、そして折り返し手綱はもう1段上、中指と薬指の間にはさんで、そして親指で抑える部分では2本をまとめている感じ。「ここですよね」指を広げて先生にジェスチャーで確認すると、「そうだね。もし持てなかったら、一緒でもいいぞ」よし、これで折り返しは解決。 じっくりウィングを観察していると、この子って簡単に首を下げていく感じ。扶助に対して素直そうに見えるし、何より軽そう。それも、ぶっとびそうな軽さじゃなくって、たぶん拍車に対しての反応がいいんだ。 これならいける、と何だか嬉しくなってしまいました。何しろ、1月の八王子での試合の敗因は、馬を前に出せなかったこと。今回はすでに、その部分を馬がクリアしてくれているんですから。あーちゃんが、「試合なんだから、自分の後のことなんか考えなくっていいんですよ。あとでどんなに馬がピリピリしちゃったっていいんだから、自分の乗る間だけちゃんと抑えられればいいんで、ガンガン前に出さないと」と言うので、さらに景気づけされた私。だんだんドキドキしてはきたけど、ずいぶん気が軽くなった。 前の競技が終わり、いよいよ自分の出る2班。前の競技者の人が下馬するのを待って、シルバーウィングに近寄ります。前の人が手綱を持っていてくれたので、鐙の長さを合わせます。前の人は背の高い男性だったので、ずいぶん長さをつめなければいけなかったけど、今日はちょっと見栄をはって長めにします。たった15分我慢できればいいんだから、Y先生の言うように鐙は長い方が評価は高いはず。 その方についでに足上げをしてもらい、騎乗。地面に落として置いた短鞭を拾ってもらい、鞍にきちんと座って折り返し手綱を持ちます。首を下げさせるための補助具だから、たぶん手綱より短めに持つのでいいんだろうと思うんだけど、とりあえず同じ長さで持っておきます。 スタッフさんが寄ってきて、「折り返し大丈夫ですか」と聞いてくれたので、「折り返し始めて持つんですけど、これでいいですか」と申告しておきます。どうせ速歩部班なんだから、折り返し持ったことがないっていうのは別に恥ずかしくないだろう。一応持ち方を指導してもらっていると、ウィングがとことこと前に出ようとします。おやおや、ちょっと止まっててよ。 全員の準備が整い、競技開始。私の前のタニノクラテ(ちなみにこの子は、昨夏の八ヶ岳ホースショーのついでに乗せてもらった馬)の発進から2歩ほど遅れて、ウィングを歩き出させました。審査員の横を通り過ぎるとき、「鞭落としましょうか」と言われ、持っていた短鞭を馬場に落とします。ってことはこの子、拍車だけでもけっこう前に出るんだな。 左手前で蹄跡に出ると、常歩から首を使って、元気良く歩くことのできる子。よしよし、いい感じ。昨日ならったハミ受けを少し試してみようと思い、手綱を左右交互に少し握ってみようとすると、右、左と握っただけでもう首が下がっています。たぶんこれは、私が求めなくても自分からハミを受ける子だ。すごいすごい。 1周するかしないうちに、「11番、折り返しもう少し長くしましょうか」と声がかかる。自分に対して言われたと思ったのだけど、私の後ろの人が返事をしたので、私じゃなかったのかな? 鞍下に番号つきのゼッケンがついていたけど、番号見なかったな。「11番」とふたたび呼びかけがあったので、やっぱり私らしい。折り返しを少し送ってみますが、慣れてないからあんまりうまくできないかも。 停止の号令がかかり、馬を止めると、いったんは止まったのですがまた動き出そうとするので抑えると、今度は腰が横に流れました。手綱持ちすぎかなー。そこへ、スタッフの人が寄ってきて、「折り返し止めますね」と、手にビニールテープ。手綱を任せると、手綱と折り返しをまとめ、ビニールテープを回して止めてくれました(左上写真参照)。これでどう持っても、手綱と同じ長さで折り返しも使えるってこと。折り返しの使い方には自信がなかったので、助かったー。 「歩度をつめ」手綱をちゃんと持って、かかとを少し内側へ向けると、すぐ反応が返ってくるウィング。「はやあーし」で、蹴るまでもなく少しかかとで押しただけで速歩が出ました。 すぐ軽速歩の号令がかかったので、軽速歩をとりますが、座る時にあんまり脚を使いすぎると前に出すぎるみたいだな。前の馬につっかかりそうになるので、少し抑えます。「2番のかた、すこし間とって」いかんいかん、勢いがあるのはいいけど、馬を抑えるのも大事なこと。部班競技なのだし。 できるだけ隅角をきっちりまわすのが高得点への近道、というのはいつも言われていることなので、隅角の手前3メートルくらいから、馬を外に出すようにこころがけます。ララミーの覆い馬場はラチが板塀になっていて、どうかすると鐙がラチをこすっちゃうかなー、というくらいまで外に出しておき、隅角に差しかかったところで内方の拍車を使い、ついでに外方脚を後ろにひいて、ほとんど巻き乗りの要領で通過。ウィングはものすごく素直に扶助についてきてくれるので、思うとおりの蹄跡が描けます。いい馬だー。 速歩に落とすと、少しハミに拳を前に持って行かれる感じ。でも、こういう馬ならきちんと持っていないと、せっかく頭下がってるんだし。拳は譲らず我慢しつつ、できる限り上体を後ろに倒します。ウィングの反動はそんなにきつくないので、正反動をとること自体はそんなにつらくありません。あと、ゆうべI野先生に言われたように、左の脚はちょっと引き気味ってくらいに引いておきます。 日の出のみんなが見ているところを通過するとき、I野先生の抑えた声で「拳空いてるぞっ」。思わずいつものクセで「はい」と言いそうになり、あわてて何事もなかった振り。馬場の外から指示を出すのは反則ですから。そう言えば昨年は、ここで「もっと前に出せ」とか言われたんじゃなかったかな。 停止の合図で止まると、きれいに1完歩で止まるのですが、止まったあとがよろしくない。前に出ようとするので抑えると、やっぱり腰が外に流れ、まっすぐ列に並んでくれません。あーもー。 斜めに手前を換え、今日は2番手なのでまさか馬が違う方向に行ってしまうことはありえませんが、斜線上の中央点で手前を合わせたあと、曲がる方向の手綱を少しだけ握っておきます。このウィングの勢いだと、タニクラにつっかかってしまいそうなので、タニクラが進入したところよりも少し手前から入り、すこし大きめに進路をとって、また少し手前から蹄跡に戻ります。斜めに手前を換えというよりも、ほとんど2湾曲だけど、仕方あるまい。 蹄跡に戻るとき、ウィングが少しだけのめってしまいましたが、ホントに1歩つまづいただけで後は何事もなかったかのように運動を続けます。よーしよし、もうちょっとだから頑張ろうね。 15分間、ウィングがあんまり軽く動いてくれるので、もしかしたら私はニヤついていたかもしれません。演技としては、蹄跡での軽速歩・速歩、斜めに手前を換えだけで、巻き乗りはありませんでした。昨日巻き乗りでいい感じだったからやりたかったのになぁ、ちっ。 常歩に落とし、蹄跡から各個に左へ、の形で馬場中央へ。馬を並べ、「お疲れさまでした」で、競技が終了。ウィングは3班目には出ないそうなので、「そのまま馬繋場へ引いていってもらえますか」とのこと。私はこの馬がかなり気に入ったので、演技終了と同時にお別れっていうんじゃなくて少し嬉しい。人なつっこくておとなしい子で、引いていく間もとても素直でした。馬繋場に近いところで、他のスタッフさんが飛んできて「すみませんでした、あとこっちでやりますんで」というので、ウィングをお返ししました。 3班目の競技が始まっているので、あわてて馬場観覧席の日の出陣地へ。 うちのカメラを預かってもらい、写真を撮ってくれていたQさんが「じっとしてない子だったねー」「うん、停止できないってので点数下がるかもね。それ以外は良かったと思うんだけど」応援で来てくれているYさんも、「I野先生が、『今日はいいなぁ、あれなら入賞狙えるぞ』って言ってたよ」と言ってくれるのですが、もちろん自分でもデキは良かったつもりですが、なんだかまた惜しくも4位になるんじゃないかという気がしなくもない。 同時進行だった駈歩部班競技が少し遅れて終わり、次は玉入れ競技。馬場の設営をやっている間に、ジムカーナの抽選がありました。私が引いたのは23番目、馬名はトウノ。順番が後ろのほうだから、経路は馬が覚えているだろう。 玉入れ競技、まず速歩班から開始。私はこの競技には出場しないので、馬付で馬場に出ます。奇しくもうちの選手のHさんが引いた馬はトウノくん。馬付をしながら、どんな馬か観察させてもらうことにしました。ところがこれが、実に重そうなんだ。私も昨年、同じ競技でボーイくんに同じことをやられているけれど、競技なのにまず速歩を出そうとしない。蹴ってもしばいても、常歩でのんびり行こうとする馬です。 少なくとも私は、Hさんより鞍数が多いんだから、同じ馬で速歩が出せませんとは言えない、言えないけど、相当苦労するだろうことは間違いない。馬から手が離れている間、I野先生にこっそり相談すると、「そうだな、拍車も鞭もガンガン使っていいぞ」ということでした。 速歩・駈歩の玉入れ競技が終わり、次はジムカーナ。これは速歩班も駈歩班も同じコースを使います。コースの下見をして、競技開始。自分の出番まではだいぶあり、それまでにトウノくんは3回コースを回ってくることになっています。 1回目、まずトウノくんがコースに慣れていないということが大きかったのでしょうが、全然速歩を出しません。コースのうち80%くらいを常歩で回ってきたトウノくん、私ホントにあれに乗るの…。次にトウノくんに乗った人は、速歩は出せていましたが、第3障害(障害じゃないけど)をトウノくんが嫌がって、外を回ってしまったり。いやーこの子、ジムカーナには向かないでしょ。 3人目の出番が済んで、控えの覆い馬場に引き上げてくると同時に、覆い馬場へ。駈歩班のあーちゃんに足上げを頼み、一緒に馬場へ入って騎乗。またがった感じはあまり大きくなくて乗りやすそうですが、いかにもおっとりしていそう。 自分の順番が呼び出されるまで、覆い馬場で少しでも速歩を出そうと思い、歩き出します。ぼちぼち駈歩班の人が入ってきているので、それをよけながら速歩を出そうとするのですが、この子はホントに重い。拍車をぐりぐり入れて、反応したなと思って速歩に移行しようとすると、そこでヘンに首を曲げて止まってしまいます。前に出ようという意思が感じられない、この子は。拍車も鞭も舌鼓も全部使って、他の馬に抜かれたときにお尻にくっつく形でようやく速歩が出せましたが、こんなに時間がかかってていいのか。 馬場の入り口のほうから、「日の出乗馬倶楽部・たかしなさん、トウノくん、控え馬場へ出てください」と呼び出しがかかりました。返事をして、馬を馬場の出口へ。馬場を出ようとすると、スタッフさんが私に「この馬、手綱持つと前に出ませんから」と注意してくれました。「あっ、そうなんですね! ありがとうございます」道理で、さっき速歩を出そうとしたときにヘンな首の曲げ方をしたわけだ。手綱が短いのがイヤだったのね。 馬場を出るところでI野先生が待っていて、馬の口をとってくれました。そのまま選手達の間を「馬通りまーす」と声をかけながら通り抜け、控え馬場へ。昨年はここでかーっとあがってしまったものですが、今年はかなり平気です。 控え馬場に入ると、私の前にはもう競技中の選手だけ。今の人が終わったら、すぐ馬場に出ることになります。あらかじめI野先生から、「馬場に入って挨拶して、ベルがなってから45秒はOKだから、スタートラインを超えないようにひとまわりしてからスタートしろ」と言われているので、その経路も含めて復習しながら待機。45秒以内に速歩が出せなかったらどうしようかな。 前の人が終わり、私とトウノくんの名前が呼ばれました。「いくよ、トウノくん」馬場に入り、競技委員長席の方を向いて挨拶。答礼してくれて、ベルがなりました。そこから経路とは違う方向に馬をすすめ、拍車を強く使って巻き乗りをすると、速歩が出ました。よかったー。そこからスタートラインまで持っていく間に、早くも常歩に落ちそうになりますが、そこは短鞭をぱちっと入れて阻止します。 スタートラインを越え、1つ目のクランクへ。障害用の横木を斜めにかけわたし、高さを出した間に入っていく感じ。トウノくんはそういうものに一切動じないのですが、もう常歩に落ちたくて仕方がないらしい。鞭を入れ舌鼓で追い、とにかく止まらせないように前へ出します。 私の前にトウノに乗った人が通り過ぎてしまった第3障害、馬も覚えているだろうから特に気をつけないと。と思っていると、やっぱり外に逃げたそうな動きをしたので、拍車を入れ「ハイ! 」と大きな声で景気をつけて前に出します。次のパイロンでの巻き乗り、ここで速歩に落としたらこの馬止まっちゃわないかな、と思いつつ、でもここで軽速歩のまま巻き乗りをするのも本式ではないので、内方の拍車を強く入れながら巻き乗り。どうにか止まらなかった。 次は横木またぎ、平行2本はまたいだことがありますが、今日のは角度があるので、少し丸めてまたがないと。そう思って横木に向かわせようとした瞬間、トウノくんがついに常歩になってしまいました。どんなに拍車を入れても、横木をまたぐときには常歩、と馬が決めているような歩き方。横木をまたぎ切ったときにもう一度声と鞭で追うと、また速歩が出ました。 次は連続パイロンでのスラローム、ここは右、左と内方を入れ替えながら進まなくてはいけません。そうすると速歩のほうが楽なのですが、スピードは全然出せない。でも方向転換には素直な子なのであまり大回りはせずにすみました。 このスラロームさえクリアしてしまえば、あとはゴールラインまでスピードを乗せるだけ。…なのですが、焦る私を知ってか知らずか、のんびり行こうとするトウノくん。もうこの子には私のあと誰も乗らないようだから、ガンガンいっちゃえ、と思って拍車もずいぶん使ったのですが、やはりマイペースのままゴールラインへ。 どうにかこうにかゴールしたとき、あまりのトウノくんの重さに、息が切れていました。 このジムカーナのタイムは82秒31。基準タイムが50秒でしたから、どんなに遅かったかってもんです。私の丸拍車は効かないので、あらかじめ誰かに棒拍車を借りておくんだったとか、長鞭も持ってきていたのに、どうして短鞭で出ちゃったんだろうとか、スタート前のひとまわりのとき、一瞬でも駈歩を出させておけばあとは軽かったんじゃないかとか、考えてもあとの祭り。私、ジムカーナ運がないのかも…。 クラブハウスに、部班競技の点数が貼り出されました。自分の点数を見ると、13点。そして名前の横に、赤のマジックで(3)と書いてあります。あれ? 上から下まで見ると、日の出のCちゃんが14点で(1)、Tさんが13.5点に(2)、Aちゃんと私にそれぞれ(3)。ということは、この赤マジックの数字は順位なんだ。やった、3位には入れた! しかも1位から3位まで日の出が独占って、いいのかしら、こんなことしちゃって。 しかし、(3)はふたつあります。3位同点2名ということになりますが、同点だとじゃんけんで順位を決めるとか言われて、じゃんけんで負けて4位とかいう展開になるんじゃないだろうな。いや、だんだん間違いない気がしてきた…。 お昼ゴハンをかっこんでいる間にジムカーナ駈歩班が終了し、残るは障害競技。ビギナーズジャンプ(H50)、小障害(H80〜100)に出る選手の馬付で、覆い馬場と控え馬場の間を走り回りました。 すべての競技が終了し、表彰式。まず社馬連班のほうから、すべての競技について表彰。それが終了してから、一般の部の表彰です。このときにはもう、クラブハウスに貼り出された成績表ですべて分かっていたのですが、速歩部班は1位・2位・3位(2名)、駈歩部班は1位・3位、速歩玉入れが1位・3位、駈歩玉入れが3位と、障害競技以外はものすごい快挙。 まず表彰は速歩部班から始まりますが、日の出のママさんがすごく心配してくれていて、社馬連の部で2位が2名いたのがそれぞれ表彰されていたので、「だいじょうぶ、3位も2名とも表彰されるわよ」と言ってくれていたのですが、3位まで表彰って言うときに、2位が2名の場合と3位が2名の場合ではちょっと話が違いそうな気がする…。 過剰な期待はしないようにしよう、じゃんけんで4位でもいいやと思っていると、ララミーの若先生から名前を呼ばれました。つづいて、Aちゃんの名前も呼ばれます。 後ろに引っ込んでいたAちゃんをひっぱって前に出ると、若先生が「3位のトロフィーは今日は1つしかないけど、もう1つ作って後日倶楽部のほうにお送りしますから、今日はどっちかね」と言ってくれました。うわー、わざわざ作ってくれるんだ。 2人揃って表彰を受け、トロフィーを受け取ります。Aちゃんはお母さんの車で来ているけど、私は帰り道は電車なので「荷物が重くなるのやだから、今日はAちゃんが持って帰って」ムリヤリ持たせ、自分は後日倶楽部に届くほうを受け取ることにしました。いやー、自分がスポーツでトロフィーもらう日が来るなんて、運動音痴の私には画期的な出来ごとでした。 |
|
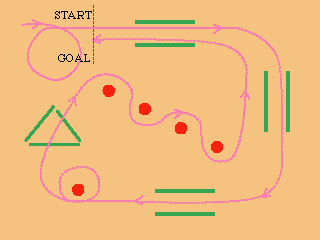 ジムカーナのコース |
||
|
今回の撮影はQさん、どうもありがとー。 |
117鞍目→ |